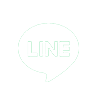- 津木 陽一郎
- 当事務所が掲げる経営理念は「笑顔ファースト」になります。
当事務所に事件をお預けして下さったすべての方々が、笑顔でいられるように当事務所のスタッフは全力を尽くします。
訴訟案件については勿論のことですが、そこまでに至らない小さなお困りごとについてもお気軽にご相談ください。皆様の笑顔を目標に精一杯のサポートをさせて頂きます。
労災で後遺障害が残ると言われた方へ
労働災害で負った怪我や疾病について、治療を続けていたものの事故前の状態に戻らなかった場合、つまり、後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害等級の認定を申請することができます。
労災事故による後遺障害について、労災保険から補償を受けるためには、労災保険に定められた障害等級認定を受ける必要があります。
後遺障害とは
労災事故により怪我を負い、労災保険による治療を進めていったとしても、症状の回復の見込みがない状態となる可能性があります。
このように、これ以上の治療継続による回復が見込めない状態を「症状固定」といい、このような状態になった場合、原則として、労災保険からの治療費の負担が終了します(療養補償給付が停止されることになり、以後、治療を継続したとしても病院の治療費は自己負担となります)。「症状固定」となった場合以後、労災保険から治療費の負担をしてもらうことはできませんが、後遺障害が残ってしまった場合には、
労災保険から「障害(補償)給付」を受けることができ、そのためには、労災保険の定める後遺障害の認定を受ける必要があります。
この認定を受けるためには、労災保険における後遺障害等級認定等の申請手続を行っていくことになります。
等級は1級〜14級まであり、認定される等級が1級違うだけで、労災保険からの給付金が100万円以上も変わってくることもあります。(1級が重く14級が最も軽い)
後遺障害の認定手続
労災保険の後遺障害等級認定を行う主体は、労働基準監督署(労基署)です。労基署の認定調査を経て、後遺障害を認定されるかどうか、認定される場合、その等級が判断されます。
この労基署に対して後遺障害等級の認定手続きを進めていくには、障害(補償)給付請求書とともに、障害の内容を具体的に記載した後遺障害診断書を一緒に提出しなければなりません。この後遺障害診断書は、ご自身の症状をできる限り詳細に記載してもらう必要があります。
しかし、主治医の先生は、治療の専門家ではありますが、必ずしも後遺障害認定の専門家ではありません。
診断書に書いてもらう傷病名、症状(痛みやしびれ)、必要な検査結果、関節の可動域について、被災者側から医師に伝えなければ、後遺障害診断書の記載に漏れが生じて適正な後遺障害等級の認定が受けられないことがあります。
被災者の後遺障害が労災において正しく認定されるためには、後遺障害診断書の作成がまず重要になります。
そして、この提出された後遺障害診断書に基づいて、労基署は被災者本人との面談を行い、後遺障害の認定について判断します(事案によっては主治医の先生に照会を行う場合もあります)。
そのため、後遺障害の認定を受けるためには、この後遺障害診断書の記載内容等が非常に重要なものになります。
この後遺障害診断書に不備や不足があることで、あるべき後遺障害等級の認定が受けられない可能性も十分にあり得ます。
当事務所のサポート
このように、後遺障害診断書の記載は非常に重要であり、記載内容によっては、認定される等級結果やその補償内容にも大きく影響が出る可能性があります。
また、ご本人が労基署で面談する際にも、初めてのことで、面談時に上手く症状等を説明できるか不安な方も多いかと思います。
当事務所は、労災被害に遭われた方の後遺障害等級申請のサポートに注力しています。適切な後遺障害診断書を作成してもらうために、症状ごとに注意すべき点や、労基署での面談時に、被災者の方が負った傷病から、ご自身の自覚症状を上手く伝えていけるように、事前に打ち合わせ等を実施しサポートさせていただきます。
労災事故に遭ってしまい、無念にも後遺障害が残遺してしまった方で、労災の後遺障害申請を控えている方、当事務所は相談無料ですので、是非事前に当事務所にご相談いただきたいと考えます。
初回
相談料0円
- 労働災害の無料相談
- 0120-955-262
- 平日9:30~17:30