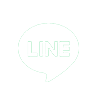- 津木 陽一郎
- 当事務所が掲げる経営理念は「笑顔ファースト」になります。
当事務所に事件をお預けして下さったすべての方々が、笑顔でいられるように当事務所のスタッフは全力を尽くします。
訴訟案件については勿論のことですが、そこまでに至らない小さなお困りごとについてもお気軽にご相談ください。皆様の笑顔を目標に精一杯のサポートをさせて頂きます。
労災認定とは
労災申請に必要な資料
労働災害に遭われた場合、療養給付(治療費の支払)や休業補償給付などの労災保険の請求をする必要があります。申請にあたっては、下記の資料を揃え、労働基準監督署に提出をする必要があります。
通常は、会社の総務部などの部署が手続きをしてくれ、必要書類を労働基準監督署に提出をしてくれます。あまり大きくない会社で総務部などの部署がない場合には、会社が外部の社会保険労務士に頼んで作成してもらう場合もあります。ただ、いずれも場合も、各申請書に労働災害に遭われた方や事業者(会社)の署名捺印が必要です。以下、各給付について、必要書類を記載します。
1.療養(補償)給付について
療養(補償)給付については、「療養の給付請求書」の提出が必要です。これは、治療費を自分で負担せずに、労災から直接病院に治療費を支払ってもらうために必要な書類です。通院先の病院だけではなく、薬の処方を受ける薬局分の提出が必要です。また、通院先の医療機関を変更する場合や、2か所以上の医療機関を並行して通院する場合には、指定病院等変更届という書類を別途提出する必要があります。
療養の給付請求書は、必要事項を記載して、治療を受けている医療機関を通して、所轄の労働基準監督署に提出します。
なお、医療機関からは、労働基準監督署へ、
通常、毎月1回のペースで診療報酬明細書(レセプト)が提出されます。レセプトは、治療回数、入通院期間、治療内容等が記載される重要書類です。左記のとおり、病院が作成して労働基準監督署に提出しますので、通常、被災者の方が目にすることはありませんが、労災認定や裁判手続などで、治療内容等が争点となった場合には、重要な証拠になります。この場合、労働局に対して保有個人情報公開請求をすることによってそのコピーを入手することができます。
2.休業(補償)給付について
休業補償給付については、「休業(補償)給付支給請求書」を提出します。
これは、労働災害による療養のために働くことができず、給料を受給できない場合に、休業(補償)給付を受けるために必要です。請求書に、必要事項を記載して、事業主および医師の証明を受けたうえで、賃金台帳、出勤簿の写し、障害年金を受給している場合にはその支給額の証明書などの必要書類を添付して、労働基準監督署に提出をします。
保険給付が決定した際には、休業開始の4日目以降について、給付基礎日額(大まかにボーナスを除いた事故前3か月の平均賃金と考えてください)の60%相当額の休業(補償)給付が支給され、あわせて同日額20%の特別支給金が給付されます。休業(補償)給付によって、およそ給料の80%が保証されることになります。なお、給付決定がされた場合には、休業補償の「支払決定通知」と「支払振込通知」が一体となったはがきが送られてきます。
3.障害(補償)給付について
治療をしても、身体や精神に一定の障害が残ってしまった場合には、障害(補償)給付を受けることができます。この場合、障害(補償)給付支給請求書に必要事項を記載して、別途通院している病院の医師に作成してもらった後遺障害診断書や、レントゲン、CT・MRIなどの画像資料などを添付して、労働基準監督署へ提出しますこの資料を基に、労働局の地方労災委員の医師が診断をする等して、後遺障害の等級認定がなされることになります。後遺障害等級が1~7級と認定された場合には、年金が支給されます(障害(補償)年金)。後遺障害等級が8~14級と認定された場合には、障害(補償)一時金が支給されます。また、社会復帰促進等事業から、等級に応じて、障害特別支給金(一時金)や、算定基礎日額(被災日の前1年間に受けた特別給与(ボーナス等)の金額を365日で割った額)を基準にした障害特別年金(1~7級の場合。8~14級の場合は障害特別一時金)も支給されます。
初回
相談料0円
- 労働災害の無料相談
- 0120-955-262
- 平日9:30~17:30